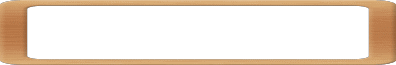ご覧の通り喫茶 大工集団 欅のデッキの上はアラレが降って白くなりました。
ログの奥に見える雲竜山は紅葉が始まりました。
アラレの白、紅葉のオレンジ、空の青。
3色がナントモ綺麗です。
冬が近づいていますね。
まだ冬支度もしていないのに・・・。
薪割り
雪囲い
畑の耕し
デッキの片付け
除雪機の試運転
・・・・
億劫になるのでもう書きません。

拡大するシニアマーケットに注目が集まる中、デビュー50周年のザ・ビートルズの全集や、結成50年のザ・ローリング・ストーンズの高音質LPの発売も予定され、アナログに郷愁を感じる中高年に加え、新たなファンを獲得しそうな勢いなのだそうです。
日本レコード協会によると、今年の1~9月のアナログディスクの生産枚数は23万8千枚で、前年同期比69%増。
邦楽は58%増ですが、洋楽に限れば96%もの増でほぼ倍増となっています。
注目のレコードも多数リリースされています。
EMIミュージック・ジャパンは14日、ビートルズの14枚組ボックスセット(5万9800円)を発売しました。
またユニバーサルミュージックは、盤面への着色をやめるなど素材から音質にこだわった「100%Pure LP」の第1弾として、12月12日にローリング・ストーンズの「スティッキー・フィンガーズ」、ジャズの巨人、ビル・エバンスの「ワルツ・フォー・デビイ」など15タイトル(各5800円)を発売するそうです。
コードを聴くにはレコードプレイヤーが必要なのですが、このプレーヤー市場も健在なのだそうです。
DENONは毎年2万台以上のアナログのレコードプレーヤーを安定的に生産しているそうです。
今時、レコードプレーヤーを買う人がいる・・・、不思議ですよね。
でも、一昨年に同社の100周年を記念して約30万円の高級プレーヤーを500台限定で発売したところ、すぐに完売したそうです。
ただ、昔と違ってレコードプレーヤーの使い方も変わってきたようです。
LPの楽曲をデジタル圧縮した「MP3」に簡単に変換できるプレーヤーが登場するなど、楽しみ方の幅も広がっているそうです。
とは言え、これではせっかくのレコードの高音質も台無しになってしまうのですが・・・。
アナログレコード市場が再拡大している理由はCDなどより音が良いことを評価する人が増えているからなのでしょうね。
私はそれにもう一つ、レコードの大きな紙のジャケットを手にする喜びも捨てがたい魅力となっています。
それにしてもレコードプレイヤーを見ていると『人間は大したものだ』と思うのです。
たったレコードの音を聴くだけなのに、このレコードプレイヤーには人類の数多くの叡知が注ぎ込まれているのですから。
レコード盤に刻まれた溝から音を取り出すのにどれほど多くの人が苦労されたか・・・。
・1000分の1秒もの狂いがなく安定した回転をするモーター。
・振動に強い駆体。
・スムーズな動きが出来て、しかも本体は動かずに先端に取り付けたカートリッジだけが動くアーム。
・微妙な溝の揺れを感じ取るカンチレバー。
・etc. etc.
レコードプレイヤーは精密器機のど真ん中ですよ。
昔の人達はよくこの様な物が作れたものだと感心します。
しかも、CDよりも音が良い。
私は今でも時々レコードを聴いています。
音楽鑑賞の主役をCDとネットの音楽配信に譲ってしまったレコードの市場ですが、ここにきて俄然熱を帯びているそうです。
今年のレコードの生産枚数(まだレコードを作っていたんですよね)は、CDより大幅に少ないとはいえ、前年同期比で7割も増加したそうです。
前回の『最近の大工集団 欅』では皆様に大変ご迷惑をお掛けし、
申し訳御座いませんでした。
今日から心機一転、また宜しくお願い致します。
発端はフィフィさんが2012年10月30日、在日外国人と生活保護に関するまとめサイトのリンクをツイッターで紹介したことでした。
この中には「年金保険料は全額免除に、生活保護の外国人」という見出しの広島県の中国新聞の記事も含まれています。
フィフィさんは「国民に相談もなしに既に決めちゃったんですか」と皮肉っぽくつぶやいた。
このツイートに対して、在日コリアンを名乗る人物が「歴史的な背景を知らないのに語る資格はないアホ」と突っかかった。
するとフィフィさんは
「在日外国人の1人として言わせていただきます。外国人が生活保護を受けること自体が不自然です。自国から拒否されてるわけで無いならなぜ愛する母国に帰らないのですか?」
と反論。
さらに「恩恵を受けているなら、文句を言うな。文句を言いながらおねだりすれば、それは"たかり"と言われても当然。プライドがあるなら自らを偽るな」と突き放した。
すると今度は別の人物が「参戦」する。
「断片的な知識しかないあなたに在日外国人を語る資格がありません。何故朝鮮半島の人々が日本に居るのか?語るなら本気になって勉強しなさい」と命令口調でした。
だがフィフィさんは「在日外国人とは表記しましたが、朝鮮半島云々とは一度も表記してませんよ?」と流す。
生活保護が一部の外国人だけを対象としているわけではないから、フィフィさんも「意見をして当然では」と投げかける。
さらに「外国人としてその国の人間と共生するとはどうあるべきかを考察している」と自説を強調した。
これに対して先の在日コリアンの人物は、フィフィさんに向けて「生まれ育ったのは日本で、帰る所なんてないんですが」「あなたが朝鮮と表記してなくても、あなたの言葉はレイシストに利用されて私達は迷惑しています」と返答。
お互いが意見をぶつけ合うもいまひとつかみ合わない様子でした。
フィフィさんは一連の議論の後で、「まともな外国人は、日本と母国の架け橋としてこの国で日本人との共生に努めています。その気が無いなら帰ればいい」と繰り返した。
これには「相互理解する気があれば共生は可能」と理解を示す人もいれば、「私のことを嫌いな人を好きになれますか」と疑問視する意見も出た。
一方で、フィフィさんに反対した在日コリアンの人物を激しくののしるツイッター利用者も少なからず見られた。
生活保護は今年、芸能人の親族による不正受給疑惑が明るみに出るなどして話題となりましたね。
2012年7月現在の生活保護の受給者は約212万人もいるそうです。
戦後間もない頃から厚生省社会局長通知で「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」とされてきた。
そこで、実際に生活保護を受けている在日外国人はどのくらいの数に上るかを調べてみました。
2010年現在、外国人で生活保護法の対象となった「被保護世帯」総数は4万29世帯で、うち韓国・朝鮮籍の人が2万7035世帯と全体の約68%を占めている。
今年にはもっと増えて約75%にもなっているだろうとのことです
では、対象となる在留資格を持つ外国人はどれほどいるのでしょうか。
法務省の統計を見ると2010年では137万5296人が該当者となり得る。
このうち韓国・朝鮮籍を持つ人は48万4025人と最多で、なかでも「特別永住者」は、全体の99%に達する39万5234人と圧倒的な数です。
生活保護、いろいろ問題はありますね。
民主党に政権が移ってからは若い働き盛りの人でも受給できるようになりましたから、増えて当たり前ですよね。
それにしてもフィフィさんのつぶやきは至極ごもっともだと思います。
エジプト出身のタレント、フィフィさんがツイッターに投稿した生活保護に関する内容が注目を集めています。
フィフィさんが日本在住の外国人が生活保護を受給するのは「不自然」だと異を唱えたのです。
これに一部の人がかみつき、さらに他のユーザーを巻き込んで議論はヒートアップしています。

第1弾は4年前にリリースされ、9人のボーカリストを収めました。
「日本人ジャズボーカリストのガイドブック的なCD」として注目を集めました。
気に入ったボーカリストを見つけ、実際にライブを見に行くなどジャズの楽しみ方が広がる一枚となったようです。
今回もルックスはもちろん実力も兼ね備えた12人のボーカリストが参加しまし。
「Lover Come Back To Me」の深澤友梨恵、「All The Way」の松浦理恵、「Stormy Weather」のサラ・レクターら才能豊かな面々がそろいました。
それにしてもジャズボーカルは女性ボーカルは人気があるのですが、男性ボーカルは人気がありませんね。
どうしてなのでしょう。
原因は・・・、女であり、男だからです。
・・・・間違いありません。
私はボーカルはあまり聴かないのですが、数少ない好きな女性ボーカリストをご紹介します。
エラ・フィッジェラルド(Ella Jane Fitzgerald 1917年4月25日 - 1996年6月15日)
最上級の賛辞が贈られるまさにジャズヴォーカルのファーストレディでした。
どんな曲でも唄いこなす抜群の安定感がある稀有の歌手でした。
ビリー・ホリデイ(Billie Holiday, 1915年4月7日 - 1959年7月17日)
その苦悩に満ちた生き様と常に対比して語られ、もはや伝説的ともなっている偉大なジャズ・シンガーです。
マヘリア・ジャクソン(Mahalia Jackson, 1911年10月26日 - 1972年1月27日)
ゴスペルにジャズやブルースの要素を入れることにより、躍動感溢れる唄として一般化したゴスペルの女王。
ジャズやゴスペル、黒人霊歌を得意とし、現在もゴスペル界最高峰の歌手として語り継がれています。
ジュディ・ガーランド(Judy Garland、1922年6月10日 - 1969年6月22日)
上の3人は黒人でブルースっぽいフィーリングがありましたが、ジュディ・ガーランドは白人で清楚な人でした。
天才少女として数々のミュージカル映画に出演しました。
抜群の歌唱力と合わせダンスも上手く、最高のエンターテイナーでした。
こうして書いてみると、やっぱり、女性ボーカルが人気なのも分かります。
こんなジャケットのCDを見たならついつい手にとって買ってしまうでしょうね。
ジャズの「J」の字も知らない人もこのCDを聴いたなら、思わずジャズクラブに行きたくなるのではないでしょうか。
国内のライブシーンで活躍する女性ボーカリストたちの作品を集めたコンピレーションアルバム「JAZZ VOCAL SHOWCASE(ジャズ・ヴォーカル・ショーケース)」の第2弾が発売されました。
今日は久々に良い天気になりました。
少なくなった晴天の日には冬支度をしなければなりません。
先日より薪割りをしていますが、店と家の2台の薪ストーブに用いる薪の量は半端ではありません。
今日も薪割りです。
アメリカのオレゴン州に住む友人から嬉しい便りがありました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私が日本を訪問した際に驚かされた点を紹介する。
日本は、まるで現代技術の周りを古き伝統が回っている万華鏡のような魅惑的な国だ。この国には、創造力、奇抜なファッション、古風な美しさ、効率的な事業、そして目もくらむファンタジーがある。日本は、全く予想もしない方法で五感を満足させてくれる場所だ。
物価は高いが、手頃な価格のサービスや製品も多い。
私の日本に対する先入観の1つに物価の高さがあり、それが訪日を先延ばしした理由の1つだった。たしかに日本は物価が高い。ギフト用の箱に入ったメロンが1個1万500円で売られている。また成田空港から東京までのタクシー代は約2万8000円もかかる。
しかし、日本には安くて便利な公共交通機関があるし、比較的安い食べ物がどこでも手に入る。デパートの地下の食料品売り場には、寿司、うなぎのかば焼き、お好み焼きなど、さまざまな食品が売っており、価格も破産するほど高いということはない。
日本人はおしゃれで、多くの人が大変創造的な身なりをしている。東京の地下鉄や大通りでは、美へのきめ細かな配慮や「人はカンバスである」との哲学が身なりに表れている人を数多く見かける。
これは東京に限ったことではない。例えば古都京都の祇園では、文字通り頭からつま先まで、伝統的な足袋と着物に身を包んだ舞妓さんたちが普通に街を歩いている。ただ通り過ぎる人々を眺めるだけでも日本をもう1度訪れる価値はある。
日本は今でもハイテク大国だ。そして、それを実感できる場所が「電気街」として知られる秋葉原だ。
秋葉原では、電器店が迷路のように立ち並び、ロボット、テレビ、ビデオゲームなど、ハイテク製品は何でも手に入るが、ここは単なる電気街ではない。
通りを歩いていると、不可解なコスチュームに身を包んだ人々に出くわす。今や秋葉原は、ハイテク、ロールプレイングゲーム、マンガなどに熱烈な関心を持つ「オタク」と呼ばれる人々のメッカとなっている。
周辺には無数のマンガ店やメイドカフェが立ち並ぶ。またフレンチ風のメイドやアニメのキャラクターの格好をした少女を数多く見かける。これは「コスプレ」と呼ばれ、彼らは好みのアニメやマンガのキャラクターのコスチュームを着て、そのキャラになりきる。秋葉原は未来と過去、ハイテクとファンタジーが融合している場所だ。
日本には、世界に類を見ない壮大な高層ビル、素晴らしい幹線道路や鉄道網が作られてきたが、一方で強力な精神が宿る荘厳な建造物も作られてきた。
東京から約50キロ離れた古都鎌倉には、これまで見てきた仏像の中で一、二を争う見事な大仏がある。また1000年もの間日本の都だった京都は、日本の他の場所と同様、現代技術と伝統という対照的な2つが共存する場所だ。京都は人口約150万人の現代的な大都市だが、このような都市は世界に類を見ない。
京都は、地域全体に数千の神社や寺があり、さらに低層の木造住宅が立ち並ぶ祇園の街がある。祇園では、顔を白く塗った芸者(京都では芸妓と呼ばれる)たちが、音楽、舞踊、茶道などの日本の伝統芸能のけいこに勤しんでいる。
また京都は、歴史、伝統芸術、古代宗教の街であると同時に、任天堂のゲーム機「Wii」や小説家、村上春樹が誕生した場所でもある。
日本人のきれい好きは、日常生活のあらゆる面に見られる。日本は白い手袋をはめている女性(たまに男性も)をよく見かける地球上で最後の場所かもしれない。また、人々が定期的に外科手術用マスクを着けている世界初の場所かもしれない。
また日本の美徳を語る上で、トイレへの言及は欠かせない。驚くべき現代技術が詰まった日本のトイレに多くの旅行者が深く感謝している。
日本の人々はどこでも、困っている外国人旅行者を見つけると喜んで助けくれるし、先入観を打ち破るような驚きを与えてくれる。そんな美的原則を重視する日本という国に対し、われわれ旅行者もありがとうという言葉とおじぎを忘れてはならない。
1950年代から1960年代後半にかけてアメリカ中を揺るがした黒人解放運動の大きな流れは音楽の世界にも当然のごとく大きな影響を与えました。
サム・クックの「ア・チェンジ・イズ・ゴナ・カム A Change Is Gonna Come」やジェームス・ブラウンの 「Say It Loud.I'm Black and I'm Proud」、それに公民権運動におけるテーマ曲的存在だった「We Shall Over Come」など、名曲は数多く存在します。
しかし、それより前の1950年以前にはそうした曲はほとんど見当たりません。
しかし、1939年という遙か昔に黒人差別の問題を直接的に訴えかける衝撃的な歌詞をもつ曲、「奇妙な果実」が存在していました。
そのうえ、その曲を歌っていた歌い手は迫害されることなく、逆にその曲は見事にヒットしたというのです。
このことに私は以前から気になっていて、なぜ10年もの空白があるのか?
その理由を知りたいと思っていました。
この疑問の答えがわかったのはつい最近のことです。
それはデヴィッド・マーゴリックによって書かれた「ビリー・ホリデイと<奇妙な果実>」という本のおかげでした。
どうやらビリーは「奇妙な果実」という曲を歌うことでいち早く1950年代への扉をこじ開けてしまったようです。
そして、もしかするとそうすることで彼女は自らの寿命を縮めてしまったのかもしれません。
ビリー・ホリデイは1915年4月7日フィラデルフィアで生まれたと言われています。
母親は未婚の母として彼女を生みますが、結局彼女は養護施設で育てられることになります。
しかし、それもほんのわずかの期間で、彼女は売春宿で働くようになっていた。
ナント14歳のとき売春の罪で投獄されています。
そしてこの頃、彼女はベッシー・スミスやルイ・アームストロングの曲と出会い、自らも歌い始めました。
こうした、彼女の悲劇的な青春時代については彼女の自伝「奇妙な果実 Lady Sings the Blues」に書かれています。(内容的な真偽については怪しい部分もあるようですが、彼女の生き様を考えると責めることはできない気がします)
歌手として本格的に活躍するようになった彼女は1920年代後半には、黒人芸能の中心地ニューヨークのハーレムで歌うようになります。
そして、1933年レコード・プロデューサーのジョン・ハモンド John Hammondが彼女の歌を気に入り、自らが育てた当時人気絶頂のベニー・グッドマンやカウント・ベイシーらの楽団と彼女を共演させます。
このチャンスを活かした彼女は一気にその知名度をあげて行きました。
当時の彼女はしっとりとしたラブ・バラードを歌う他のジャズ・ヴォーカリストたちと歌う曲に関しては大差ありませんでした。
しかし、その表現力に関しては謎に包まれたその悲惨な生い立ちの影響があったのか、他のアーティストたちとは違う優れたものをもっていました。
だからこそ彼女は、ニューヨークで当時話題のナイト・クラブ「カフェ・ソサエティ」の専属歌手という地位を得ることができたのです。
実は「カフェ・ソサエティ」の存在こそ、ビリー・ホリデイと「奇妙な果実」の出会いの場であり、その曲が歌われることが許された数少ない場所のひとつでもありました。
早すぎたはずの歴史的名曲を守り、育て、世界へと広める「孵化器」の役目を担ったのが「カフェ・ソサエティ」だったのです。
「カフェ・ソサエティ」とは、やり手の靴のセールスマン、バーニー・ジョセフソンという人物がグリニッチ・ビレッジにあったもぐり酒場を改装してオープンさせたナイト・クラブでした。
その店の常連客は知識人、作家、各界の有名人、進歩的な学生、芸術家など様々でしたが、けっして気取った上流階級のための店ではなく、逆に急進派、左派、自由主義者たちなどが集まる進歩的な雰囲気に満ちあふれた店でした。
そのため、店内には黒人も自由に出入りでき、当時としては珍しい画期的な存在でした。
女性のヌードを見せ物にすることもなく、みだらなギャグを聞かせることもなく、白人に迎合する黒人たちのショーを売り物にすることもない、そんな当時としては珍しいナイト・クラブでした。
その常連客の中には、チャーリー・チャップリン、エロール・フリン、ローレン・バコール、リリアン・ヘルマン、ラングストン・ヒューズなど、一癖二癖ある有名人たちもいました。
こうした、進歩的な素晴らしい観客に恵まれたからこそ、「奇妙な果実」という過激な歌は1930年代という早い時期に存在しえたわけです。
もちろん、この歴史的名曲を作ったこれまた時代の先を行く人物の存在もまた、この名曲の誕生物語にとって重要なのは言うまでもありません。
「奇妙な果実」の存在は有名でも、意外とにその作者の名前は知られていないようです。
それは、一時期ビリー・ホリデイがこの曲の詞を作ったのは自分だと言っていたりしたせいかもしれませんし、それが白人だったせいかもしれません。
ブロンクスにある高校で教師として働いていた白人のエイベル・ミーアポルは妻とともに共産党に入党していました。
しかし、当時アメリカで共産党員であることは、社会的な地位を維持するためには秘密にする必要がありました。
その後、マッカーシーによる赤狩りが始まると、さらに彼らは危険な状況に追い込まれますが、二人は秘密共産党員として活動を続けています。
しかし、ミーアポルの隠された顔はそれだけではありませんでした。
彼にはルイス・アランというもうひとつの名前、ペンネームがありました。
彼はこの名前を用いて「作家」「作曲家」「詩人」としての仕事をしており、そうして稼いだ中から共産党に寄付をし続けていました。
彼は数多くのミュージカルや芝居の台本を書き、その後教師をやめてからは映画などの音楽を専門に作曲する作家として活躍することになります。(ビリーの自叙伝「奇妙な果実」には、彼の名前は偽名のルイス・アランとして登場しています)
ミーアポルは進歩的な人物だったこともあり人種問題にはもともと関心を持っていました。
しかし、ある日公民権運動の雑誌を見ていて、大きな衝撃を受けます。
それは、南部のどこかで写された写真で、リンチをされてぶら下げられた黒人の無惨な姿が写されていました。
当時、すでに黒人がリンチにあうことは減っており、珍しいことになりつつありましたが、未だにアメリカ国内でこうしたことが行われていることを知った彼は、その時の思いを一編の詩に込めました。
その詩のタイトルは「苦い果実 (Bitter Fruits)」でした。
彼は自らこの詩に曲をつけ、彼の妻や黒人の歌い手たちに歌ってもらうようになります。
当初その発表の場は、あくまで仲間内の集まりに限られていました。
しかし、しだいにその曲は評判になり、政治的な集会などの場でも歌われるようになります。
そして、ある時前述のカフェ・ソサエティのオーナー、バーニー・ジョセフソンがこの曲を耳にしました。
ある日ミーアポルは、ジョセフソンに呼ばれてカフェ・ソサエティを訪れます。
そして、ビリー・ホリデイの前でピアノを弾きながら「苦い果実」を歌ってみせました。
初め彼女はそれほどその歌を歌うことに対し積極的ではなかったようです。
その曲は歌詞は衝撃的ではあっても、曲自体はそれほど目新しいものではなく、彼女にとってそう魅力的には映らなかったのかもしれません。
しかし、その後彼女がある小さなパーティーでその歌を歌ったところ、その場にいた人たちが感動し、是非それを歌うべきだと彼女に勧めてくれました。
こうして、ついに彼女はその曲を自分のレパートリーに加える決意を固めたのでした。
黒人の虐殺が日常茶飯事であったこの当時、それを告発する歌を黒人女性が歌うのはあまりにも危険なことでした。
ここでその後のカフェ・ソサエティにてについて書きましょう。
1939年のある日、その歌は初めてカフェ・ソサエティの舞台上で披露されました。
彼女が歌い終わると観客席ではしばらく沈黙が続き、その後拍手がわき起こり、人々は口々に彼女の歌を讃えました。
何の偏見ももたず、素直に芸術を愛することのできる素晴らしい聴衆に見守られこの曲は幸福なデビューを飾ることができたのでした。
もちろん、オーナーのジョセフソンは、その曲にちょっとした演出を加えていました。
彼女のステージにおいて、常にこの曲はラストを飾ることになり、その後彼女はいっさいアンコールを受けず、そのまま歩いてステージを降りるようになります。
さらにこの歌を歌うとき、明かりのほとんどは消され彼女にスポットをあてることで観客の心を歌に集中させ、うるさい観客は店から追い出す場合もあるなど、徹底的に曲の雰囲気作りにこだわりました。
こうして、「奇妙な果実」は彼女のテーマ曲的な存在となり、カフェ・ソサエティの人気とともにその名がしだいに店の外、ニューヨークから全米へと広がって行きました。
カフェ・ソサエティとともに有名になった「奇妙な果実」でしたが、そのままでは歴史的名曲と呼ばれるまでにはならなかったはずです。
より多くの人に聞かせるためには、やはりレコード化が必要でした。
しかし、この曲のレコーディングについて、彼女の所属するコロンビアはあまりに内容が過激であるとして及び腰でした。
この曲をレコード化して発売することは、コロンビア・レコードが抱える南部の顧客たちを敵に回すことが明らかだったからです。
そして、もうひとつプロデューサーのジョン・ハモンドが、「奇妙な果実」という曲を気に入っていなかったからでもありました。
その曲は、けっしてジャズっぽくなく、メロディーが美しいわけでもなかったことから、ビリーにはむいていないと思ったからでした。
実際「奇妙な果実」が発売された当初、このレコードが売れたのは、カップリングされていたもう一つの曲「ファイン・アンド・メロー (Fine and Mellow)」のおかげだったとも言われています。
結局、この曲は左翼系の小さなレーベル、コモドア・レコードによって録音、発売されることになりました。
しかし、レコード化はされたものの、弱小レーベルからの発売では販促活動もままならず、当初は販売エリアもごく小さな範囲に限られていました。
そのうえ、ラジオ局はこのあまりに刺激的な歌詞の曲をかけようとしなかったため、その存在を知らせるには一部の雑誌や口コミに頼るしかありませんでした。
そんなわけで、このレコードは1945年までの5年間で5万枚程度の販売枚数にとどまっていました。(もちろん、当時のレコード販売枚数からすれば十分ヒットと呼べる枚数ではありましたが・・・)
彼女は「奇妙な果実」のおかげでいよいよその人気はピークに達し、アーティストとして充実した時期を迎えようとしていました。
しかしその反面、私生活の方は母親の死や暴力によって彼女を虐待し続けた男の存在などによりボロボロの状態になっていました。
すでにマリファナとアルコールにどっぷりつかっていた彼女は、1940年代に入るとより習慣性の強いヘロインに手を出すようになります。
1947年には、ついに麻薬治療のためにニューヨークの病院に入院しますが、そこから抜け出すことはできず、ついに麻薬の不法所持で逮捕されてしまいます。
ペンシルヴァニアの連邦刑務所に収監された彼女は、そこで一年近く過ごして後に出所しますが、すでに彼女にかつての面影はなく、ふくよかだった肉体はげっそりと痩せ衰え、ダブダブの衣装を来た彼女の姿を見て多くの観客が「死」を予感するようになりました。
1959年2月彼女はイギリスに渡り、テレビ放映用のコンサートに出演しました。
その時「奇妙な果実」を歌った彼女の鬼気迫る姿は、まるでその曲で歌われている木からぶら下げられた腐りかけの死体を思わせるほどの迫力だったといいます。
すでに彼女の精神と肉体はギリギリのところまで来ていました。
1959年5月、昏睡状態でニューヨーク市内の病院に運ばれます。
3ヶ月後の7月17日、病院の廊下に放置されたままの遺体を看護婦が発見。
享年44歳でした。
「奇妙な果実」は、有名な曲の割にはあまりカバーされていません。
実際彼女が歌っていた当時、その曲をカバーしていたのは黒人フォーク・シンガーのジョシュ・ホワイトぐらいで、その後1960年代にニーナ・シモンがカバーして以降、しばらく目立ったカバーは現れませんでした。
この曲はあまりに暗く直接すぎる内容であったため、かえって黒人アーティストには敬遠されるようになってしまったようです。
そのためか、1980年代以降逆に白人のアーティストたちがこの曲をカバーするようになりました。
UB40(1980年)、スージー&ザ・バンシーズ(1987年)、スティング(1986年)、ロバート・ワイアット(1986年)など、彼らによってカバーされることで、リンチによって殺された黒人たちのことを歌っていた曲は、より広い範囲の差別と暴力についての曲へと変身をとげたと言えるのかもしれません。
その分、かつての毒気は薄められてしまったのかもしれませんが、同じ黒人ジャズ・ヴォーカリスト、カサンドラ・ウイルソンのカバーは十分に刺激的な歌に仕上げられています
ここで「奇妙な果実」のもつ意味を考えてみましょう。
1960年代末にピークを迎えることになる公民権運動。
この歌はやがて黒人への暴力に対する反対運動を代表する歌となりました。
この歌詞によって心に植えつけられた暗鬱なイメージこそが、20年後に公民権運動という輝かしい果実を結ぶ種子の一つとなったのです。
「奇妙な果実」は、20年近く前にその運動を先取りする形でニューヨークから全米へと拡がり始めました。
ビリー・ホリデイは、『「奇妙な果実」は頑固な偏見をもつ人と真っ直ぐな人をわける力がある』と言いました。
確かに一度でもこの曲を聴いたことがある人で、良識をもつ人なら、その後公民権運動が拡がりをみせた時、迷うことなく人種差別に対し「No ! 」と言ったかもしれません。
歴史の流れは急激な変化を見せるように思えても、その底流にはもっと長い周期をもつゆったりとした流れもあり、静かに少しずつ時代を変え続けているのではないでしょうか。
「奇妙な果実」は、「進歩的なカフェのオーナーと客たち」それと「時代を先取りする優れたソング・ライター」、この奇跡的な出会いによって、生まれた時代を揺り動かす静かなる革命宣言だったのかもしれません。
歌詞
Southern trees bear strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root
Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees.
Pastoral scene of the gallant south
The bulging eyes and the twisted mouth
Scent of magnolias sweet and fresh
Then the sudden smell of burning flesh.
Here is a fruit for the crows to pluck
For the rain to gather for the wind to suck
For the sun to rot for the trees to drop
Here is a strange and bitter crop.
訳詞
南部の木には奇妙な果実がなる
葉には血が、根にも血を滴たらせ
南部の風に揺らいでいる黒い死体
ポプラの木に吊るされている奇妙な果実
美しい南部の田園に
飛び出した眼、苦痛に歪む口
マグノリアの甘く新鮮な香りが
突然肉の焼け焦げている臭いに変わる
カラスに突つかれ
雨に打たれ 風に弄ばれ
太陽に朽ちて 落ちていく果実
奇妙で悲惨な果実
ビリー・ホリディは基本的に一人で育ったようなもので、誰にも愛されずにいた彼女の少女時代に受けたトラウマが彼女の人生を決めると共に、そうした心の奥底からの淋しさが誰にも真似ることの出来ない魂の叫びとでもいえる彼女の歌を作り出したのには間違いありません。
聴けば解ると思いますが、スタンダードを歌っているときでも、彼女の魔力がかったヴォーカルは、曲を彼女の歌以外の何物でもないものに変えてしまいます。
ビリー・ホリディはしゃがれた低い声で、音程の高低差もあまりはっきりせず、お世辞にも上手いとは言えません。
しかし、胸に迫る説得力が確かにある。
ビリー・ホリディはジャズシンガーということになっていますがブルースシンガーといった方がいいかもしれないと私は思います。
現在の軽いノリのジャズシンガー達から比べるとなんともけだるい声がまとわりつくように耳にこびりついて離れないのです。
前置きが長くなりました。
今日は彼女の代表曲「奇妙な果実(Strange Fruit)」について書きたかったのでした。
20世紀のポピュラー音楽の歴史をながめていると、そこには社会の変化に連動して、生まれるべくして生まれた歴史的なヒット曲が存在することに気づかされます。
そんな歴史的名曲の中でも、一際輝きを放つ作品、それがビリー・ホリデイの代表曲である「奇妙な果実」です。
18日に日本人の女性ボーカルCDをご紹介したのですが、私はジャズ・ボーカルは殆ど聴きません。
今日はその例外の一人であるビリー・ホリデイ(Billie Holiday, 1915年4月7日 - 1959年7月17日)を少し長くなりますが書かせてください。
彼女は「レディ・デイ」と呼ばれるジャズ史上最も高名な女性シンガーでした。
彼女については書きたいことが山程あり、今までにも何度か書きました。
私がビリー・ホリディに興味を持ったのは大学時代に知り合ったアメリカ人留学生がビリー・ホリディの自伝を読んで感動した部分を話してくれたからでした。
それは・・・。
【ビリーは、禁酒法時代のハーレムの真ん中で、非合法のナイトクラブに出入りするようになった。
大量のアルコールと朝まで響きわたるジャズ。
ビリーは無一文で、住むところも追い立てられる状況の中、地元のクラブで「Body & Soul (身も心も)」を歌った。
観客からは拍手はなかった。
ナイトクラブはシーンと静まりかえり、観客は皆、涙していたのです。】
コレを聞いて私は彼女のアルバム「アラバマに星落ちて(SONG FOR DISTINGUE LOVERS)」を買いました。
それまでに聞いたことがない歌唱でした。
皆涙したと言うのが理解できます。
ああ、何のために落ち葉を拾い集めて持ってきたかというと、堆肥にするためです。
堆肥にして畑に入れるのです。
堆肥にするのには落ち葉・粉糠・ヤギの糞等を入れます。
狭い畑ですが化学肥料を使わずに作物を作っています。
昨日は木曜日で喫茶 大工集団 欅の定休日でした。
一週間に1日の休みは意外と忙しく、昨日は落ち葉を取りに行ってきました。
例年ならば白峰の奥の別当出合あたりまでブナの落ち葉を取りに行くのですが、今年は取りに行くのが遅くなり道路が冬期閉鎖となっていました。
その為にUターンをしてスーパー林道の入口にある蛇谷の自然観察園まで取りに行きました。
道路横の側溝に入っている落ち葉を集めて袋に入れて取ってきたのですが、人間って欲が出るもので袋の上に乗って嵩を減らして少しでも多く持ってくる努力をしたのでした。
それから20年後のこの再会セッションでは、サイドメンもボブ・ジェームス(Bob James)、ジョン・スコフィールド(John Scofield)、ロン・カーター(Ron Carter)、ハービー・メイソン(Harvey Mason)などと今様ジャズメンが務めています。
それもあってか、単なる懐旧趣味に終わらず、温故知新というか、正に「Old Wine in New Bottles」を地で行く嬉しい演奏が満載です。
こんなに楽しくブレンドされたアルバムもそうはありません。
マリガンの作曲家としての魅力、シワシワの顔になったのと引き換えに別人のように吹きまくるようになったチェット、フリージャズからシフトチェンジしたばかりのボブ・ジェイムス、そしてデイヴ・サミュエルズの爽やかなヴァイブ・サウンド。
そしてロン・カーターは・・・、いつもの調子。
注目はこのアルバムがレコーディング・デビューのジョン・スコフィールドです。
早くも「アウト」フレージングしています。
しかし最大の大穴はハーヴェイ・メイソンのトニー・ウィリアムスも真っ青なスーパー・ドラミングでしょう。
ここでの演奏は本当に凄い。
音色、フレージング、グルーヴ、どれをとっても完璧です。
こんな凄い「ジャズ」ドラミングをしていたのに、どうして完全にフュージョンに行っちゃったんでしょう。
このアルバムはコンパクトに新旧世代の良さが詰め込まれているだけでなく、同時に「ジャズドラム裏名盤」候補の筆頭に挙げられる大変に大変にお得なアルバムだと思います。
お得と言えばこのアルバムにはもう一つお得があります。
昔、レコードでは2枚組みで出ていたものが、CDでは1枚になり、レコードを買った身としてはかなりお買い得といえます。
1974年の今日、チェット・ベイカー(Chet Baker)と、シバェリー・マリガン(Gerry Mulligan)とが伝統あるカーネギー・ホールに出演しました。
その時のライブ盤が、「Carnegie Hall Concert」です。
この二人は50年代に双頭バンドを組んだ中であり、例えば「The Complete Pacific Jazz Recordings of Gerry Mulligan Quartet with Chet Baker」等で、その相性の良さが発揮されています。
もう秋は過ぎて冬になったのかもしれません。
もっとも11月7日が立冬だったのですから暦の上ではとっくに冬なのですがね。
今朝、初霜が降りていました。
デッキの床は白くなっており、金魚鉢にも初氷が見られました。
冬なんですね。
でも、まだ冬支度が終わっていません。
薪割りも残っていますし、雪囲いもしなければなりません。
木にも雪囲いを・・・。
そうそう、デッキの上のテーブル等も片付けなくてはなりません。
除雪機の試運転。
ヤギ小屋に波板を取付なくては。
融雪管の点検。
板塀の取り外し。
・・・・・・・・・・・・・・・・。
冬さん、もう少し遅く来て下さい。
助数詞は、それだけで何を指しているかが読み取れる日本の優れた文化とも考えられます。
一葉とあれば写真だと分かるし、一棹とあれば羊羹だと分かります。
ほかの言語ではこうはいきません。
ところが、現代ではどんなものも一枚や一個で済ませてしまう人も少なくありません。
もはや助数詞は絶滅寸前です。
一枚でも十分に意味は伝わるうえ、相手を不快にさせる言葉遣いでもないから見過ごしてきた人がほとんどでしょう。
でも、相手が言葉遣いにうるさい人ならどうでしょうか。
酒席で「一杯どうぞ」と言ってしまったら、耳を傾けてはくれないかもしれません。
「一献(こん)どうぞ」ですよね。
でも現代で「一献どうぞ」と言う人は少ないでしょう。
でも、こういう時代だからこそ逆に、正確に口にすれば高評価を得られる可能性があります。
せっかくの日本の良き文化を眠らせておくのはもったいない。
とっさの会話でも正しく使えるように、日頃から正しい数え方に慣れておきたいものですね。
海にいる烏賊(いか)は、形で数え方が決まり、烏賊は、杯(さかずき)に似ています、そこで、「一杯(ぱい)」「二杯」と言うのだそうです。
他には、「どんぶり」・「船」も形が似ているので、「一杯」だそうです。
箪笥(たんす)は、運び方で数え方が決まったそうです。
昔、箪笥は持ち運べるように上に金具が付いていました。
そこに、竿を入れ、運んだので、「一竿(さお)」だそうです。
昔の人は、意味のある数え方を作っていたのですね。
意味までは、知りませんでした・・・(汗)
そして、スゴイのは魚の「鮪(まぐろ)」の数え方です。
海で泳いでいる時から、私達の口の中に入るまで、数え方が変わるのです。
これには、びっくりしました!
海で、泳いでいる時は・・・「一匹」
漁師さんが、水揚げすると・・・「一本」
それを、半身に切ると・・・「一丁」
また、半分にすると・・・「一塊」
お寿司屋さんに来て、切ると・・・「一さく」(漢字を忘れました)
それを、一人一人に・・・「一切れ」ずつ切り、
口の中へ入るのは寿司「一貫」。
マア、現代のストアでは「1パック」という、数え方もありますね(?)。
さて、私も日本人の大人として、正しい数え方をしているのか?と言えば・・・、声が小さくなります。
日本語が乱れている現代になったと言われ久しくなりました。
大人が正しい日本語を使い、子供達に正しく伝えていかないともっともっと正しい日本語が減っていくと、自分の反省も含め感じています。
写真なら一葉(よう)、羊羹(ようかん)なら一棹(さお)という具合に物には正しい数え方がありますよね。
日本語では物の数量を数えるときに付ける“助数詞”が、物の種類別にきちんと決められています。
鮨は一貫、椅子は一脚、海苔は十枚で一帖というように助数詞は多数あり、500種類もあると聞きました。
今朝ふと気づいたことがあります。
大工集団 欅では家を建てています。
喫茶 大工集団 欅では珈琲を点てています。
同じ「たてる」なんですよね。
そんなことを考えていたら先日お客様と話していたことが思い出されました。
単位についてです。
今日は私の友人、黒川進をご紹介します。
彼を分かってもらうには逸話を書けばいい思います。
ある年、友人達と骨休めに旅館に宿泊しました。
男4人がすることは麻雀でした。
夕食の御膳が運ばれてきたのですが、彼はこう言うのです。
「ワシはかぁか(妻)の作った物しか食わん」
とうとう彼はご馳走には一箸も手を付けませんでした。
さて、麻雀を一休みして温泉に入ろうとなったときに、彼はこう言うのです。
「ワシの裸はかぁかにしか見せん」
とうとう彼は温泉には入りませんでした。
温泉に入り麻雀を再開して夜中の3時に終わりました。
後は寝るだけです。
その時、彼は奥さんに電話をして迎えに来いと言っているのです。
「ワシはかぁかの横でしか寝ん」
夜中に奥さんが迎えに来られました。
こんな事もありました。
夜、彼の家を訪ねると食事中でした。
奥さんは台所に立って彼の食事を見ていました。
彼が「ご馳走さん」と言ったのですが、どの食器にも料理がたくさん残っています。
私が「料理を残すのは行儀が悪いぞ」と言うと、彼はこう言ったのです。
「ワシが残さんとかぁかの食うもんがないがや」
いやー、驚きました。
趣味は鮎の友釣りです。
手取川で釣りをするから来いと言うのでついて行きました。
お昼近くになって奥さんが弁当を持って川に来ました。
どおしてここにいるのが分かったのだろうと不思議で彼に聞いたら、
「下からずーっと探して来るんや」と言うではありませんか。
彼のような旦那をもつと奥さんは苦労するなーと思いました。
パチンコをして3万円以上勝つと上にぎり寿司の折り詰めを買ってきてくれました。
ある時、「かあーぁかと出掛けてパチンコ屋に寄ったら、出たり入ったりで6時間も・・・」と言うので、
「奥さんもパチンコをするのか?」と聞いたら、
「いや、いつも車の中で待っとるんや」と言う。
6時間も車の中で・・・。
「養子のくせにもっと奥さんを大切にしろ」と言ったら、
「これ以上、大事に出来るか」と言いやがった。
そんな頑固な彼が昨日の早朝に永眠した。
最愛の奥さんに手をさすられながら息を引き取りました。
黒川進、私はあなたの友人になれて幸せです。
とうとう12月になってしまいましたね。
今日12月3日は明治5年までは元旦でした。
明治政府は1872(明治5)年11月9日にそれまでの天保暦を廃し、太陽暦を採用する旨を布告しました。
太陽暦の採用で1872年(明治5)12月3日が明治6年(1872)1月1日にりました。
明治という時代には何かしら明るいイメージがあるのは私だけではないと思います。
犬山の明治村を歩いているだけで楽しくなるのは何故なのでしょう。
その理由は、明治にはそれまでとは違った新しい多くの文化が日本に入ってきてそれまでとは違った出来事があたったからです。
太陽暦の採用もその一つです。
明治という時代のおかげで日本国が植民地にならなかったと思います。
元号が明治に変わったからと言って世の中すべてが変わった訳ではないでしょうが、30数年で日清、日露の対戦に勝利し、極東の小国が世界に名乗り出られたのも明治の人々のおかげです。
他のアジア諸国と異なり植民地にならなかったのは、いち早く西欧化したことが大きな要因です。
その中の一つが改暦です。
アジアは農暦により大きな文化圏を形成しておりましたが、我が国は西欧化のため1872(明治5)年11月9日それまでの天保暦を廃し太陽暦を採用する旨を布告しました。
一説によれば、明治政府はこれにより12月分の給料の支払いを免れたほか、翌年の明治6年は旧暦では閏年にあたるので、旧暦を継続していれば13ヶ月分の給料が必要だったことになります。
(旧暦の閏年は1年が13ヶ月になります。今年平成24年は新旧ともに閏年でした)
ところが、コレが問題なのです。
山の持ち主が分からないのです。
市役所の吉野支所では○○さんではないかと教えてもらったのですが・・・。
どおも違うらしいのです。
さてさて、どうしたものでしょうか。
今日は一日中雪が降りそうで、屋根雪が落ちると大変なことになります。
持ち主に言わずに切り倒すよりしょうがないようです。
昔、『木立の中に家を建てたい』と思っていました。
木立の中の小動物を見ながら、木立の葉が風でこすれる音を聞いて暮らしたいと考えていたのです。
それは現実的に叶わず、今ここで木立の中ではなく横で暮らしているのですが・・・。
こんなこともあるのですから木立の中のとはとんでもない発想でした。
ところで、左の写真をご覧下さい。
裏山のクルミの木が折れて屋根に倒れ込んでしまいました。
夜中にゴソっという音がしたときに倒れたのだとおもうのですが、・・・。
本格的な雪となりましたね。
白山吉野の積雪は・・・、35㎝です。
今年はデッキの上に積雪高が分かるように、10㎝単位の印を付けた棒を立てました。
さてさて、今年の冬の積雪はどこまでゆくのでしょうか。
レイチェルカーソンの「沈黙の春」、ローマクラブの「成長の限界」に次ぐ警告の書といわれた「奪われし未来」が96年に出版されてまもなく10年を迎えました。
日本語版も97年に初版が、そして01年には改訂版が出され多くの反響を巻き起こし、まさに衝撃の一冊となりました。
私は今になって読みました。
衝撃的な内容に驚きの連続でした。
ここ60年ほどの間に人類は、薬品やプラスチックなどの合成化学物質を10万種類ほど作りだして環境にばらまいてきました。
これらの物質は元々自然界にないものなのでなかなか分解されずにいつまでも残ります。
いまや北極圏からサハラ砂漠、深海底にいたるまでこれらの物質が検出されない場所はありません。
これらの科学物質のなかには、動物の体内に入るとホルモンと似たような働きをしたり、反対にホルモンを遮断したりして動物のホルモンバランスを崩してしまうものがあるのだそうです。
人も含めた動物は発生から誕生、成長する過程でとてもホルモンに影響されていることがわかってきました。
とくに、発生直後に胎内で極微量の擬似ホルモンを浴びただけで、その動物は誕生してもすぐ死んでしまったり、障害を持って生まれてきたり、成長しても生殖機能が発育しなかったり、癌になったり、あるいは体は無事でも行動面に影響が出て知能が劣ったり、多動症だったり注意散漫だったり、ストレスに過剰反応したりするという。
そしてこの動物に影響を与える量(濃度)というのが一兆分の一(ppt)単位なのだそうです。
つまり妊婦が薬を服むとか服まないの問題じゃなく、ペットボトル入りのジュースを飲んだだけでも、そのペットボトルの成分が溶け出してそれが有害なものなら影響を受ける可能性がある、ということなのです。
人類はこれまでDDTやPCB、ダイオキシンなどについてはその危険性に気づいて製造を禁止したり、これ以上出さないように注意していますが、これは成人が癌になるかどうかを基準にして調べてわかったことで、これから生まれてくる子供たちがそれらの物質でどうなるのかは全然考えてこなかった。
しかし世界的に人も含めた動物に異変が現れているのは事実です。
ところが、これらの影響を調べようにも10万種類もある合成化学物質が、どういう風に動物の体内で作用するかを調べられるはずもないし、まして人のように寿命が長い動物が成長してから障害が現れたりしても、それが果たして自然なものなのか、母親の胎内でどれかの化学物質に極微量だが曝されてしまったからなのかを調べるのはかなりむずかしい。
実際不可能なのです。
製薬会社にしてもプラスチック製造会社、素材製造会社にしても製品の成分を公表する気持ちはないし、どの合成化学物質のどんな成分が動物に影響を与えるかもまだわかっていない。
それに自然界に放出されて残留している合成化学物質(環境ホルモン)どうしが複雑に化学反応する可能性もある。
もうお手上げ状態なのです。
この本が出版されてもう10年以上もたつのに一時話題になっただけで、その後環境ホルモンを増やさないために合成化学物質を規制しようとか、目だった動きは全然聞こえてきません。
地球温暖化の問題も世界が足並みを揃えての解決が一向に見えませんね。
地球規模の問題は国々それぞれの考え方の違いがあり、解決は遅々として進みません。
環境ホルモンの問題は個人でできることなどほとんどないと思いますが、私はせめて除草剤などは使わないようにしようと思い、そうしています。
これらの物質は分解されずに動物の脂肪層に残り、食物連鎖の上位にいる動物ほど溜め込んでいるのでなるべく下位のものを食べるようにしようと思います。
現代の医学は癌にばかり気を取られていますが、癌は発症した人の命だけの問題(それでも大きな問題なのですが)ですが、環境ホルモンは人類だけではなく、生物全ての命に関わる問題です。
読み進めると『ゾー』っとしたのは私だけではないでしょう。
雪が降り続き、連続3日間も除雪しています。
一年ぶりの雪景色はやはり綺麗です。
さて、今日は恐ろしい本をご紹介します。
と言ってもオカルトや恐怖本ではありません。
環境ホルモンについての化学本なのですが、一般の人にも理解しやすいように読みやすく書かれています。
科学探偵物語という副題がついた環境警告本です。
本の題名は
『奪われし未来』
(Our Stolen Future" by Theo Colborn, Dianne Dumanoski, Johon Peterson
Myers)
シーア・コルボーン、ダイアン・ダマノスキ、ジョン・ピーターソン・ マイヤーズ著

1枚のLPはすべて同じ時の演奏というのが一般的ですが、1950年代には異なるセッションをまとめて1枚にしているLPアルバムがよくありました。
これは、もともとSPレコードや、10インチLPのために収録された音源を、後に標準フォーマットとなった12インチ(30センチ)LPにまとめたためです。
要するに長時間収録ができるフォーマットができたので、それ以前のものをまとめて収録したというものです。
でも、タイトルを新たに付けずに、その中のひとつを流用したものも多く、当然内容とズレが出ます。
『ソニー・ロリンズ・ウィズ・ザ・モダン・ジャズ・カルテット』はその典型例なのです。
タイトルは収録された3つのセッションのうちのひとつですが、半数以上はソニー・ロリンズ・カルテットの演奏です。
しかもこのアルバムが彼の記念すべき初リーダー・セッションなのです。
『ソニー・ロリンズ・ファースト・アルバム』としていればずいぶん印象も変わっていたはずなのですがね。
51年のディグでイースト・コーストの若きバッパーたちが吠えたとき、彼らは不況の中であえぎながらも黒人ならではのジャズの可能性を追求する覚悟を決めたのではないでしょうか。
マイルス、ロリンズ、マックリーン、彼らはいずれも若く、豊かな才能を持っていました。
ロリンズはスタン・ゲッツ、ズート・シムズといった実力派の白人奏者と大きく異なる、独自のトーンで、斬新そのもののソロを繰り広げていました。
本作で競演のM.J.Qはジョン・ルイスといういわゆるホワイト・ニグロ的感性をもったリーダーとミルト・ジャクソンという、ソウルの塊のような個性が共存するユニットでした。
そこで奔放なロリンズが吹きまくっているのです。
早熟ながら、すでにロリンズの完成された個性は『On a Slow Boat to China』や『Mambo Bounce』でエキゾチックな楽想をも自分のテンポとアドリブで料理しています。
初リーダー・アルバムとは思えない堂々とした見事な演奏です。
このレコードには51年2回と53年のセッションの3つのセッションが収められていますが、いずれもモダン・ジャズの古典といえるほど素晴らしい内容に仕上がっています。
このアルバムから天才ロリンズの快進撃は始まったのです。
奇しくも今日は、1951年の12月17日、この『ソニー・ロリンズ・ウィズ・ザ・モダン・ジャズ・カルテット』の録音がされた日です。
そんなことを考えていると一つのアルバムを思い出しました。
『ソニー・ロリンズ・ウィズ・ザ・モダン・ジャズ・カルテット』(Sonny Rollins With The Modern Jazz Quartet)です。
衆議院選挙は自民党の圧勝でしたね。
経済問題、外交問題等々多くの問題がありますが、庶民の私は暮らしやすい世の中になって欲しいと願うばかりです。
さて、今日の話題は・・・。
今でも40年から50、いや60年前のジャズアルバムを聴く人が多くいます。
私もその一人なのですが、レコードを持っているアルバムでもCDを買うことがあります。
それは何故かというと録音の長さなのです。
LPレコードは片面20分、両面でも40分しか録音できませんでした。
CDは80分の録音が可能です。
(ユニヴァーサル・クラシックス・レーベルの”PANORAMA”の中のブラームス作品集のDisc2のパッケージには「80分15秒」と記載されているものの、実際にプレイヤーにかけると「80分17秒」と表示されるそうです)
その為に、以前に2枚組のレコードで発売されていたアルバムがCDで1枚に収まって発売されていることがあるのです。
LPでは音楽に浸っている時に何度もレコードをセットしなければならず、興ざめになることが多くありますが、CDではそのまま一挙に聴けるため重宝します。
ところでビル・エバンスにはVerve期の盤としては、『Trio '65』というアルバムもあります。
このアルバムの録音は1965年2月3日でタイトルと一致しています。
どちらも名盤ですよね。
やはり、『ビル・エバンスに駄作無し』ですね。
録音の時期からするとライブならば納得なんですが、スタジオ録音なのに、しかも発売はクリスマスを過ぎてからなのに、クリスマス・ソング『4 Santa
Claus Is Coming to Town』などというお遊びの曲も録音しています。
それでもこのアルバムはジャズ喫茶で人気がありました。
やはり、Gary Peacockが付き合ったというのが特徴となる演奏です。
標題とは違って、実際には63年暮れの録音なので、時節柄もあって「4 Santa Claus Is Coming to Town」などというお遊びもしています。
元盤は8曲構成でしたが、CD化に際してでしょうか、65年録音のオケ伴演奏、「Trio with Symphony Orchestra」盤を9以下に付加しています。
実はこのアルバムはタイトルとは違って1963年の今日12月15日に録音されました。
何故Trio '64なのでしょう?
このアルバムには珍しくゲイリー・ピーコック(Gary Peacock)が付き合っています。
予想されるようなコンビネーションの良さが嬉しいアルバムです。
CDには、オーケストラ付きのトラックがオマケで付いています。
今日も昨日に引き続きジャズアルバムの話しをしましょう。
ジャズのアルバムにはタイトルを間違ったのでは?と思われるものが時々あります。
ビル・エバンス(Bill Evans)の『Trio '64』もそうなのです。